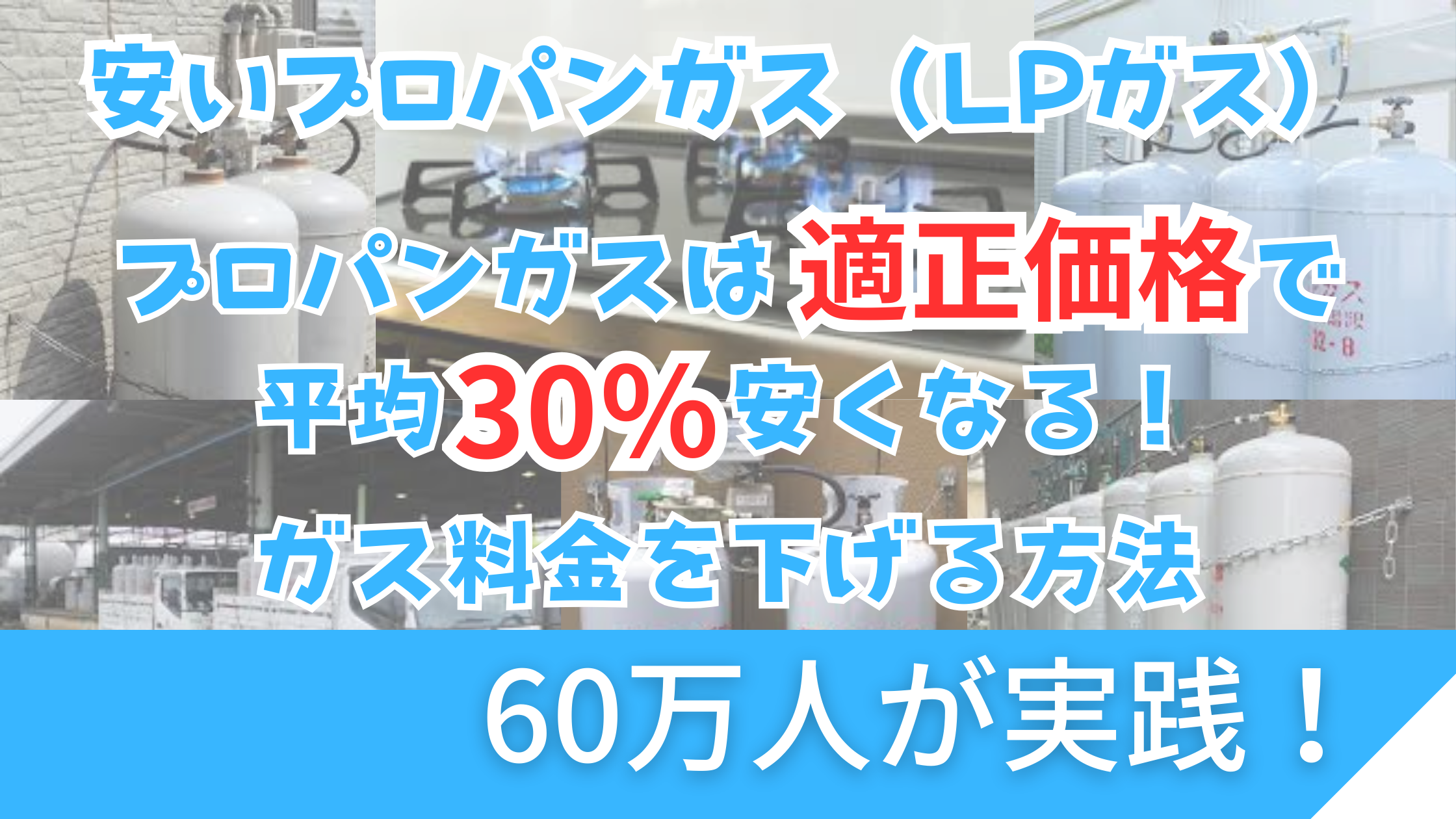エネピで料金比較
最短3分で最安プラン発見

料金消費者協会
切替手続きを無料代行

適正化協会
ガス会社ご紹介
バルク供給とは(LPボンベとの違い)
LPガスバルクの見た目について

LPガスのバルク供給とは、ガスを大量に貯蔵できる大型タンク(バルク貯槽)を設置し、タンクローリー車から直接ガスを補充する方式です。
LPガスボンベの見た目について
従来一般的なボンベ(容器)供給は、20~50kg程度のシリンダー容器が空になれば満タンの容器と交換する方法でした。

これにより配送の効率化と安定供給を図れます。
例えば従来は輸入基地→充填所→ボンベ配送という手順が必要でしたが、バルクなら充填所を介さず軒先での直接充填が可能となりました。
容量の違いも大きな特徴です。
50kgボンベ1本のガス容量は約25㎥(立方メートル)ですが、大型バルクタンクはその数倍~数十倍のLPガスを貯蔵できます。
使用量の少ない一般家庭では依然ボンベ供給が多い一方、集合住宅や飲食店、大規模施設ではバルク貯槽が設置されるケースが増えています。
バルクとボンベの根本的な違いは貯蔵量と供給方法であり、バルクは大量ガスをまとめて扱える分、ガス事業者による定期補充と監視体制が組まれます。
ボンベは可搬性が高く交換容易ですが、バルクは据置きで交換はできないため遠隔監視システムによる残量チェックや計画配送がセットで運用されます。
個人宅・業務用などにおける設置・運用(利点と課題)
バルク貯槽は一般戸建住宅から商業施設、公共施設まで設置が可能です。
設置に際しては、法令で定められた容器と建物・敷地境界との離隔距離や基礎コンクリートへの固定(アンカーボルト止め)などの安全基準を満たす必要があります。
小型(内容量数百リットル程度)のバルクタンクなら戸建て敷地にも設置でき、地下埋設タイプも存在するため景観に配慮した設置も可能です。
例えば集合住宅の屋外に50kgボンベが何本も並んでいたスペースを、1基のバルクタンクに置き換えることで設置面積を削減できた事例もあります
(※地下埋設を含め柔軟な配置が可能)。
バルクの利点(メリット)

安定供給と合理化
一度に大量のLPガスを補充できるため配送頻度が減り、在庫切れのリスク低減と物流コスト削減につながります。
配送車の走行回数が減ることで騒音や排ガスも抑制され、環境負荷軽減にも寄与します。
また電話回線や通信を用いた遠隔残量監視により、ガス不足や異常を早期に検知し計画的な充填が可能です。
保安の高度化
バルク貯槽は盗難・イタズラ防止のため充填口が施錠可能な鋼製プロテクターで覆われ、地震時にはマイコンメーターが自動遮断するなど多重の安全装置が組み込まれています。
容器交換時のヒューマンエラーもなくなり、ガス漏れ検知器や緊急遮断弁と組み合わせて高い安全性を確保できます。
実際、震度5以上の地震で自動的にガスを遮断する装置や過大流量時にガスを止めるヒューズ栓など、家庭向けバルクにも標準装備されています。
美観・省スペース
ボンベが林立する代わりにタンク1基で済むため見た目がすっきりします。
専用フェンスやカバーで覆えば住宅地でも違和感が少なく、土地の有効活用につながります。
コストメリット
ガス使用量が多い場合、バルク化による配送効率向上分がガス料金に反映され、単価引き下げにつながるケースもあります。
事業者側も配送コスト削減メリットがあるため、大口需要家ではボンベ供給より有利な料金提案が可能です。
バルクの課題(デメリット)

一方、導入・運用にあたって次ような課題も指摘されます。
初期コストと設備スペース
バルク貯槽本体は容量にもよりますが数十万~数百万円と高価で、基礎工事費や配管工事費も含めるとボンベ方式より初期投資が大きくなります。
例えば内容量約500kgのバルクタンクで100万円強、約1トンで180万円前後の価格帯(税別)。
個人宅向けの場合、多額の設備費用を誰が負担するか(ガス事業者による無償貸与か購入か)も検討が必要です。
また設置には平坦で安全なスペースが求められ、都市部の狭小地では確保が難しい場合もあります。
需要規模との適合について
バルクは一定以上のガス消費量がある場合にメリットを発揮します。
使用量が少ない家庭だとタンク内のガス回転率が低く事業者にとって非効率となるため、小口需要には従来ボンベが適するケースが多いです。
したがって戸建てでも暖房や給湯でLPガスを多用する住宅、あるいは集合住宅など年間使用量が大きいユーザーでないと導入メリットは出にくいです。
供給事業者への依存
バルク貯槽は設置後の充填・保守を契約事業者に委ねる形となり、ボンベのように容易に他社へ切替えることができません(タンク設備が事業者所有の場合が多い)。
このため契約先選定にあたってはガス料金だけでなく保守サービス体制や長期的な費用も考慮する必要があります。
法定検査・メンテ
バルクタンクは高圧ガス設備として定期点検・検査義務があります。
設置容量によっては容器検査や耐圧検査の記録管理、ガス事業所としての届け出など専門的対応が必要です。
事業者が代行するとはいえ、ユーザー側もそのスケジュールに協力しなければなりません。特に容量が大きい(概ね1トン超)貯槽では耐震設計に基づく基礎工事や行政への申請手続きも伴うため、導入ハードルは高めです。
もっとも近年は、500kg未満の小型バルクも普及し始めており、プロパンガス利用の集合住宅オーナーが入居者サービス向上(ガス料金低減)目的でバルク化する例や、寒冷地の戸建住宅で冬期の頻繁なボンベ交換を避けるためバルクを採用する例も見られます。
導入にあたっては使用量・設置条件を踏まえ、ボンベとの費用対効果を十分比較検討することが重要です。
災害時の非常用活用と災害対応型バルクシステム
LPガスは分散型エネルギーであり、個別供給ゆえに大規模災害時でも各需要家ごとにエネルギーを確保しやすいという強みがあります
都市ガスのように供給本管が被災すれば全戸停止しますが、LPガスは各施設ごとに独立した貯蔵があるため、設備が無事ならすぐ利用再開が可能です。
過去の震災でもその復旧の早さが注目されており、例えば2011年の東日本大震災では仙台市内に設置されていた災害対応バルクが地震・津波被害を受けつつも安全点検後ただちに使用再開でき、耐震性の高さを実証しています。
また2018年北海道胆振東部地震で約40時間の大停電に見舞われた函館市の病院も、前年にLPガス災害バルクシステムを導入していたことで長時間にわたり自立発電を継続できたと報告されています。
このように「非常時に災害に強いエネルギー源」としてLPガスバルクが再評価されています。
自治体でも学校体育館など避難所となる施設にLPガス設備を導入し、停電時でも照明や空調が使える避難所づくりを進める動きがあります。
特に近年注目されるのが「災害対応型LPガスバルク供給システム」です。

これは平常時は通常のガス供給設備として機能しつつ、災害発生時には貯槽に備蓄されたLPガスを用いて炊き出しや給湯、暖房、発電を行えるよう工夫されたシステムです。
具体的には、LPガスを貯める「バルク貯槽ユニット」と、用途に応じた「供給ユニット」(調理用コンロ・炊飯器、湯沸かしボイラー、ガス発電機・照明等)を組み合わせて構成されます。
非常時にはこれらユニットを接続するだけで、避難所で温かい食事の提供や給湯、ストーブによる暖房、さらにはLPガス発電機による電源供給(スマートフォン充電や照明点灯など)**が可能となります。
平時からLPガスを利用している施設であれば「備蓄燃料が常に循環している」状態のため、常に一定量以上のエネルギーが確保されている点も利点です。
例えば北九州市内に設置された500kg貯槽では、貯槽内ガスが最低レベル(残量15%程度)で被災した場合でも、大型炊き出しコンロ1台なら約200時間、1.5kVA(1500W相当)の発電機1台なら約300時間連続運転できるガス量を備えていると試算されています。
複数機器を同時使用する場合でも数十時間の稼働が可能で、ライフライン途絶直後から避難者の生命線を支えることができます。
災害対応型LPガスバルクシステムの設置例(公共施設の屋外に設置された500kgバルク貯槽を安全柵で保護し、「火気厳禁」「無断立入禁止」の表示がなされている)
※平常時は給湯や空調に利用され、非常時は非常用燃料供給設備となる
「災害対応バルク」は各地で導入が進んでおり、避難所となり得る学校、公民館、福祉施設などに数多く設置されています。
既存のバルク貯槽でも後付けで非常用ユニットを増設すれば同様の機能を持たせることができ、自治体施設や病院、介護施設等で導入が拡大しています。また企業が自社の従業員避難拠点確保のため設置したり、地域の自主防災組織と協定を結んで地域防災拠点として活用するケースもあります。
2025年度の補助金・支援制度
災害に強いLPガス設備の導入を後押しするため、政府および関係団体はいくつかの補助・支援制度を用意しています。中でも代表的なのが経済産業省資源エネルギー庁が実施する**「災害時に備えた社会的重要インフラへの自衛的な燃料備蓄の推進事業費補助金」です。これは病院や避難所等へのLPガス災害対応バルクや石油タンクの導入費用**の一部を補助する国費事業で、令和5年度以降毎年数十億円規模の予算が計上されています。補助対象は以下の通りで、2024年度(令和6年度)もエルピーガス振興センターを執行団体として公募・交付が行われました。
対象施設
災害時にライフライン維持が必要な社会的重要インフラ施設。具体的には、①多数の避難困難者がいる病院・老人福祉施設等、②指定避難所など地方公共団体が災害時に避難場所とする公共施設、③一時避難所となり得る民間施設(学校、幼稚園、公民館、企業オフィス、工場、ホテル、商業施設等)で、地方自治体と「被災時に施設を避難所として提供する協定」を締結しているもの。※大規模災害時に危険が及ぶ施設(LPガス充填所等)や協定未締結の民間施設は対象外。
対象設備
LPガス災害バルク等(LPガスバルク貯槽とその調整器類)およびLPガス非常用機器。に定義されるように、容量300kg~3tクラスのバルク貯槽または50kg容器×8本以上の集合容器設備を備え、さらに非常用の燃焼機器ユニット(LPガス発電・照明ユニット、炊き出し用調理ユニット、LPガス給湯ユニット等)を1つ以上組み合わせたものが補助対象となります。平常時のライフラインが止まっても独立稼働できることが条件で、例えば給湯ユニットならポンプや発電機も組み合わせ停電時でも稼働できる構成が必要です。
補助率・金額
補助率は基本1/2(中小企業等は2/3)で、上限額は設備内容により段階的です。目安として、容器・供給設備のみの場合最大1,000万円、発電機やGHP(ガスヒートポンプ空調)等も同時導入する場合は3,000万円、さらに複数の非常用機器を組み合わせる包括的な設備導入では最大5,000万円まで補助されます。補助対象経費には貯槽・機器の購入費だけでなく設置工事費も含まれます。実質的に設備費用の半額程度を国費で賄えるため、地方自治体や医療法人などにとって導入ハードルを大きく下げる効果があります。
申請・採択
毎年度、公募期間が設定され応募申請が行われます。令和6年度実績では5月下旬~6月中旬に電子申請受付が行われました。申請には事前に地方公共団体との避難所協定締結や、導入計画の策定が必要です。採択後はエルピーガス振興センターの指導のもと工事を実施し、実績報告・検査を経て補助金が交付されます。最新の公募情報や手引きは振興センターの公式サイトで公開されており、令和7年度(2025年度)も同様のスケジュールで募集が行われる見込みです。
2025年度に利用可能な主な補助制度
| 補助制度名称(年度) | 対象者・対象施設 | 補助内容(率・上限額) | 申請方法・期間(目安) |
|---|---|---|---|
| 社会的重要インフラ自衛的燃料備蓄推進事業補助金(令和7年度) (LPガス災害バルク・石油タンク導入支援) | 病院、老人ホーム等「避難困難者施設」 指定避難所・福祉避難所等の公共施設 一時避難所となる学校・民間施設(協定締結済み) | 設備費・工事費の1/2補助(中小は2/3) ※上限:設備構成に応じ1,000万~5,000万円 | 毎年公募(例: 5月~6月頃受付) 執行団体(LPガス振興センター)へ計画申請 |
| その他自治体独自支援(例) 東京都LPガス非常用発電設備助成 | 地方自治体によって異なる(防災拠点施設、地域町会等) | 例:LPガス発電機購入費等への助成(上限数百万円規模) | 各自治体の防災担当課に随時申請 (自治体予算に依存) |
※上記の国補助金のほか、一部自治体では地域防災力向上を目的にLPガス非常用発電機や簡易バルク設備導入への助成制度を設ける例もあります(東京都など)。
詳細は各自治体の防災・エネルギー施策公募要項を参照してください。
導入事例と設置先の効果
LPガスバルク及び災害対応システムの実際の導入事例をいくつか紹介します。
こうした設備は医療・福祉分野から教育施設、民間企業まで幅広く採用されており、それぞれ災害時に大きな効果を発揮しています。
医療施設(透析クリニック・病院)
福岡県糸島市の伊都クリニックでは、非常用電源としてLPガス設備を導入しました。その結果、災害発生時でも人工透析治療を継続可能になるという安心感を得ています。同院は補助制度を活用して非常用発電機付のバルク貯槽とガス空調(GHP)を導入しており、停電時でも電力と温水を供給できる体制を整備しました。また群馬県前橋市のある総合病院でも、災害対策としてLPガスコージェネレーション(25kW×8台)と3tバルク貯槽を設置しています。平常時は病院のエネルギーコスト削減に寄与し、有事には非常用電力と給湯をまかなえる多様なエネルギー源として機能しています。病院関係者からは「停電への備えとエネルギー多様化による安心感が得られた」との声が出ています。
介護・福祉施設
長野県松本市のニチイケアセンター松本寿(デイサービス施設)では500kg級の災害対応バルクを導入し、非常時の避難者受入れ拠点に備えていますj-lpgas.gr.jp。新潟県上越市の特別養護老人ホームではLPガス非常用発電機とバルクを組み合わせ、停電時も施設内暖房や医療機器が稼働可能な体制を構築しました(自衛的燃料備蓄補助金を活用)。これにより利用者の安全確保に万全を期しています。
教育施設(学校・幼稚園)
東京都東大和市では市内中学校の体育館空調にLPガス式GHPエアコンを採用しました。各中学校体育館は地域の指定避難所となっており、「規模が大きく市内に分散しているため、災害に強いLPガスが適当」と判断されたものです。導入後、平時の空調費削減に加え停電時でも稼働する避難所として住民に安心感を提供しています。ほかにも長野県白馬村の保育園(幼稚園)では災害対応バルクとガス炊飯器を備え、非常時に園児・職員への炊き出しや暖房が確保できるようになりましたj-lpgas.gr.jp。郡山市の開成学園(学校法人)でもLPガスバルク・非常用発電設備を導入し、防災力強化とBCP(事業継続計画)の両面で効果を上げていますj-lpgas.gr.jp。
公共施設(自治体庁舎・公民館)
自治体では庁舎や地域の公民館等にも導入例があります。茨城県境町役場では災害公営住宅に併設するコミュニティ施設へLPガス非常用発電設備を導入し、町全体の防災拠点ネットワークの一翼を担っています。栃木県真岡市の関根町公民館では地域住民と協力して災害対応型バルクを設置し、自治会主体で炊き出し訓練等にも活用されています。仙台市若林区の大願寺(寺院)では、寺を開放した避難所運営を想定してLPガスバルクとガス機器を備蓄しており、東日本大震災級の地震でも設備が稼働した実績がありますj-lpgas.gr.jpj-lpgas.gr.jp。
商業施設・企業
旅館やホテルなど宿泊施設でも非常用エネルギー源としてLPガスバルクを導入する例がありますj-lpgas.gr.jp。長期滞留者への炊き出しや電力提供が可能となり、防災付加価値が評価されています。また日本コークス販売株式会社など企業の倉庫・事業所でも災害バルクを設置し、従業員と地域住民の一時避難所として機能できるよう備えていますj-lpgas.gr.jp。これら企業では平時の自家発電併用で省エネ効果も得ています。
こうした導入事例の蓄積により、2021年時点で全国1,173か所にLPガス災害対応バルクが設置されています。内訳は医療・福祉施設638か所、公的避難所127か所、その他一時避難所となり得る施設408か所に上り、年々その数は増加傾向です。導入先からは「停電復旧を待たずに避難所運営が開始できた」「非常時の初動が円滑になり地域住民に安心感を与えた」「平常時もエネルギーコスト削減に役立っている」等の評価が報告されています。LPガスバルクは災害時のエネルギーセキュリティ確保のみならず、平時のエネルギー供給の効率化や環境負荷軽減にも貢献するインフラとして定着しつつあると言えます。
主なLPガスバルク製品とメーカー比較
LPガスバルク貯槽を製造・提供するメーカーはいくつか存在します。
国内で代表的なメーカーとしては、I・T・O株式会社(伊藤工機)、神鋼機器工業株式会社(エスケイシリンダー)、矢崎エナジーシステム株式会社、中国工業株式会社、富士工器株式会社などが挙げられます
これらメーカーはそれぞれ多様な容量・仕様のバルク貯槽をラインナップしており、安全機構や付帯設備にも特色を持っています。
また、大手エネルギー企業の**岩谷産業株式会社(イワタニ)**などは自社でタンク製造は行わないものの、各メーカー製バルク貯槽を組み込んだシステム提案やメンテナンスサービスを提供しています。
主要メーカーの製品仕様や特徴比較
| メーカー(ブランド)j-lpgas.gr.jp | 容量ラインナップ | 主な仕様・特徴 | 安全性・耐震性への配慮 | 参考価格帯(税別) |
|---|---|---|---|---|
| I・T・O株式会社 (イトー)j-lpgas.gr.jp | 約0.2~2.9トン(内容積417~7036リットル) (170T型~2900型まで縦型・横型を展開) | ・ユニット化出荷: 工場で調整器や安全弁を取付けたユニット状態で納品可能。現地工事は低圧配管接続のみで簡便。 ・縦型(T)と横型(Y)を選択可能。 ・小型(417L)から大型(7036L)までサイズ多彩itokoki.co.jp。 | ・安全弁や緊急遮断装置を完備。 ・大容量(3t級)は別途耐震基礎設計が必要okayasanso.co.jp。 ・アンカーボルト固定による耐震計算書を用意(500kg型等)skcylinder.co.jp。 | 500kg:約110万円 980kg:約170~180万円e-net.takasho-inc.co.jp ※設置工事費別途 |
| 神鋼機器工業(SKシリンダー) (旧神戸製鋼系)j-lpgas.gr.jp | 約0.15~2.9トン(150kgから2.9tまで) (家庭用小型から大型業務用まで) | ・高精度溶接技術: 国内自社工場での精密溶接により信頼性確保。 ・温水式・電気式貯槽(BAiO): 外部加熱でベーパーライザー不要とし寒冷地でも安定気化。 ・取付脚部を工夫し現地施工性向上。 | ・フランジ部をガスケット+Oリングのダブルシール構造とし微漏洩防止。 ・安全弁元バルブに業界初のボール弁採用で確実な遮断。 ・耐震固定用のアンカー計算書を公表(例:500kg型)し、適切な据付施工を推奨。 | 500kg級:100万円前後 1トン級:150~200万円程度 (※実売想定、容量比例) |
| 矢崎エナジーシステム (ヤザキ)j-lpgas.gr.jp | 0.3~1トン程度(主に災害対応バルク向け規格品) | ・災害対応バルクシステム開発: バルク貯槽+供給ユニットをパッケージ化し非常時に簡易接続できる製品を提供。 ・自社でガスメーターやマイコンメーターも製造しており、一体的な防災システム提案が可能。 | ・災害対応製品は全て専用架台に固定済みで出荷され、設置先で耐震性確保が容易j-lpgas.gr.jp。 ・津波被害を受けた実機が性能を維持した実績あり(仙台市)j-lpgas.gr.jp。 | (個別見積) ※導入規模・ユニット構成による |
| 岩谷産業(イワタニ) (サービス提供者) | 500kg~5トン(他社製タンクをプラン提案) | ・ガス大手によるトータル提案: バルク貯槽から発電機・GHP空調まで組み合わせ、設計・施工・アフターを一括提供。 ・遠隔監視サービス: 24時間365日の有人監視で残量・異常を見守り、故障予兆も早期発見。 ・高圧ガス保安協会と連携した検査・保安体制。 | ・全国対応の保安要員ネットワークで災害時も迅速対応。 ・大規模災害時にはLPガスの機動補給(ボンベ・ローリー両面)も可能な体制。 | (提案内容による) ※ガス料金に設備償却含め月額課金 |
※備考上記価格帯はタンク本体の目安で、基礎工事・配管・附属機器費用は含みません。
設置工事・保守を含む総合サポート事業者
LPガスバルク設備の導入には、製品販売だけでなく設置工事や保守点検をトータルに請け負う事業者の存在が不可欠です。
幸い、日本全国に約1万を超えるLPガス販売事業者があり、その多くがバルク供給に対応した技術資格者(液化石油ガス設備士、高圧ガス販売主任者など)を擁しています。
これらのような企業・団体が総合的なサービスを提供しています。
- 大手エネルギー企業系列
- 前述の岩谷産業(IWATANI)のほか、
- 伊藤忠エネクス
- ENEOSグローブ
- 大阪ガスLPG(ガスパル等)
- 東京ガスリキッドホールディングス(TOKYOGAS LPG)など
- 大手商社・石油会社・都市ガス会社系列のLPガス販売会社は、全国規模でバルク供給サービス網を構築しています。
それらは自社でバルクローリー車隊を保有し、需給監視センターによる遠隔見守り、定期点検・緊急対応の24時間受付など万全のサポート体制を敷いています。
例えば大阪ガス系列のガスパルでは自社保有の「災害対応バルク・ユニット」を複数持ち、平時から設置先に燃料を備蓄しておくことで有事に即応できる仕組みをとっています。
その他の事業者
地域密着のLPガス販売店
各都道府県のLPガス協会に加盟する地場のガス店も、近年バルク供給への移行を進めています。こうした事業者は戸建住宅や中小規模施設向けの設置工事実績が豊富で、ユーザー宅の事情に合わせた柔軟な対応が可能です。たとえば新見ガス株式会社(岡山県)では個人住宅の庭先にも設置可能なコンパクトバルクを提案し、専用フェンスで美観と安全性を確保する工事を行っています。保安点検も含めワンストップ対応し、利用者から「ボンベ交換の手間が無くなり安心して使える」と好評です。
設備工事会社(メーカー系代理店)
I・T・Oや神鋼機器工業などメーカー直系の販売代理店・工事会社も存在し、工場出荷から設置まで一貫して対応します。これらは主に業務用・公共物件の大規模案件を扱い、ゼネコンや設備設計事務所と連携してバルク設備を組み込んだ建築プロジェクトを進めています。また必要に応じて法定検査の代行や行政手続のサポートも行い、ユーザー側の負担軽減に努めています。
LPガス振興センター等の相談窓口
一般財団法人エルピーガス振興センターや日本LPガス団体協議会(日団協)は、補助金情報提供や導入相談を受け付けています。公式サイトでは災害対応バルクの導入事例集や指定機器一覧を公開しており、希望者はそれらを参考にしつつ最寄りの登録事業者を紹介してもらうこともできます。
※特に補助金を利用する場合、申請手続きを熟知した事業者のサポートが成功のカギとなるため、振興センターの公募説明会資料などを活用して信頼できる施工業者を選定することが推奨されます。
なお、個人宅向けの場合はガス料金とのバランスも重要です。
多くのLPガス販売店はバルクタンク設置費を自社負担する代わりに契約期間中のガス料金で回収するビジネスモデルを取ります。このためユーザーは長期契約が求められますが、その分初期費用0円でバルクのメリットを享受できます。事業者選びの際は料金メニュー(従量単価・基本料金)、保安サービス内容、緊急時対応力などを比較し、総合的に信頼できるパートナーを選ぶことが大切です。
災害対応型バルク設備の保安収納例。バルクタンクと調整器類一式を金属製キャビネット内に収め、施錠管理することで防火安全性と防犯性を高めている(北九州市 内の公民館設置例)
総じて、LPガスバルクの導入は平時の利便性向上と災害時のレジリエンス強化の二面で大きなメリットがあります。
ボンベ供給との違いを正しく理解し、信頼性の高い情報源を参照しながら計画を立てることで、家庭や施設のエネルギーをより安全・安心なものにできるでしょう。
各種補助制度も活用しつつ、地域の実情に合ったLPガスバルク活用策を検討してみてください。
参考文献・情報源 本調査レポートは経済産業省・資源エネルギー庁、公的団体(LPガス振興センター・日本LPガス協会等)ならびにメーカー各社の公開資料

エネピで料金比較
最短3分で最安プラン発見

料金消費者協会
切替手続きを無料代行

適正化協会
ガス会社ご紹介